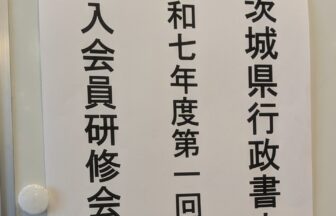用排水路をまたぐ橋や渡り板──茨城県でよくある「占用+維持協定」とは?

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
私たちが住む茨城県の農村部では、家の前や農地の出入り口に小さな橋や渡り板がかかっている風景をよく見かけます。
「これって誰の土地?」「勝手にかけていいの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はこうした橋や暗渠は、農業用水路(法定外公共物)を“占用”している状態になる場合があります。
しかも、単に「占用許可」を取るだけでなく、維持管理に関する協定が必要になるのがポイントです。
🔹 用排水路の正体:「法定外公共物」
農村地帯の水路は、昔から地域で使われてきた**法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)**にあたるものが多いです。
つまり、国や県、市町村が“管理者”ではあるものの、地元の土地改良区や水利組合が実質的に管理しているケースが一般的です。
そのため、占用の申請をする際には
- 行政(市町村や県)への占用許可申請
- 土地改良区などとの協議・同意書の取得
- 維持管理の覚書(協定書)締結
といった“3段階”の調整が必要になることもあります。
🔹 よくある事例(茨城県内)
茨城県内の中でも、筑西市、桜川市、つくば市、石岡市などの旧農村地域では、次のような事例が頻繁です。
- 宅地造成で、排水路をまたぐための小橋を設置
→ 家や駐車場への出入りのための橋を設けるケース。
→ 「コンクリート桁+鉄板」など簡易構造でも占用対象。 - 農地間の出入りのための渡り板
→ 農機が通るための鉄板橋。
→ 仮設でも“恒常的使用”とみなされれば占用。 - 用水路の上に設けた通路や通学路
→ 町内会・学校が設ける歩道橋も対象になることがある。 - 宅地開発で既存の水路を暗渠化(埋設)して利用
→ 水路の形状を変える場合、土地改良区との調整が必須。
🔹 「占用許可」だけで終わらない理由
占用許可が出たとしても、**「維持は占用者の責任」**というのが基本ルールです。
橋や暗渠が壊れて通水に支障が出れば、水利組合や土地改良区から補修を求められることになります。
そのため、実務上は「維持協定(覚書)」という形で次のような取り決めを行います。
- 構造物の維持・修繕は占用者が行う
- 通水機能を妨げないよう管理する
- 壊れた場合は速やかに撤去・補修する
これらを文書で交わしておくことで、トラブル防止につながります。
🔹 無許可のまま設置してしまうと…
「昔からかけてあるから」「隣の人もやってるから」で設置したままにしておくと、
・農業用水の流れを妨げる
・落下事故などの危険がある
などの理由で、行政や土地改良区から撤去を求められることもあります。
特に、建築確認や相続登記の際に「水路の越境がある」と指摘されることも。
最近では、売買・相続時のトラブルとしても注目されています。
🔹 行政書士にできるサポート
行政書士としては、次のようなサポートが可能です。
- 水路占用許可申請書の作成・提出代行
- 土地改良区との協議書・同意書の取得
- 維持協定書の作成・調整
- 現地測量図・位置図の添付サポート
単なる「申請書作成」ではなく、関係者調整を含めたコーディネートが重要です。
🔹 まとめ:占用は「使うこと」だけでなく「責任を持つこと」
用排水路をまたぐ構造物は、誰かが“勝手に”作ったものではなく、
本来は管理者の許可と、維持する責任を伴うものです。
「ただの橋」でも、
・誰が管理しているのか
・どの範囲まで自分の責任なのか
をはっきりさせておくことで、地域トラブルを防ぐことができます。
昔のままだからといって、そのままで良い時代ではなくなってきています。
手続きは平日しかできないことも多くあります。
貴重な時間を割くよりも、行政書士くぼや事務所にまるっとお任せ!
どうぞお気軽に、お問い合わせください。