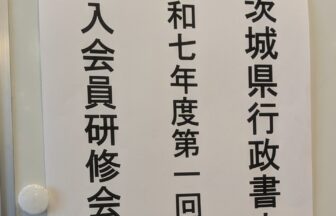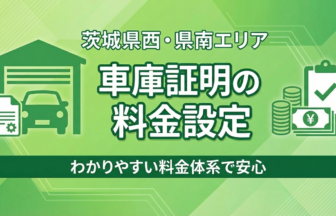普段なにげなく通っている道路。実は、道路の上や下を個人や企業が使うには「道路占用許可」が必要なことをご存じですか?
電柱や水道管のようなイメージが強いですが、実は「え?これも占用なの?」というケースがたくさんあります。
この記事では、行政書士の視点から、ちょっとマニアックな道路占用の事例を10個ご紹介します。
道路占用とは?
「道路占用」とは、道路法第32条に基づき、道路の上や下に工作物や施設を設置して継続的に使用することをいいます。許可を出すのは、その道路を管理している国や県、市町村などの「道路管理者」です。
占用には必ず許可が必要で、無断で物を設置した場合は撤去命令や占用料の追徴を受けることもあります。
一般の人には意外?珍しい道路占用10選
① 家の前の植木鉢やプランター

玄関先に並べている植木鉢。少しでも道路の境界を超えると占用にあたることがあります。見た目はきれいでも、通行の妨げになれば撤去対象になることも。
② 道路側にはみ出したポスト・表札

塀の外に設置したポストや表札も要注意。基礎部分が道路にかかると占用扱いになる場合があります。建て替え時に「位置を戻してください」と指導されるケースも。
③ 店舗前ののぼり旗・看板

お店の前に立てるA型看板やのぼり旗。歩道にはみ出していると、短期間でも道路占用に該当します。
イベントやセール時は特に注意が必要です。
④ 駐車場の車止め・チェーンポール

敷地出入口にあるチェーンポールやスイングゲート。基礎が歩道に少しかかっているだけでも占用対象になります。
設置時は境界確認をしっかりと。
⑤ 自治会の防犯カメラや街灯

防犯目的でも、電柱や道路上に設置するカメラや街灯は占用物です。市や警察との協議、そして占用許可が必要になります。
役場で勤務していた頃、これらの申請手続きを多く経験していました。
行政書士が申請をサポートできる分野です。
⑥ 地下に埋めた給排水管・電気配線

店舗やアパート工事で、道路下に管を通す場合は「地下占用」として許可が必要。
図面付きで申請しなければならず、無許可工事は後に撤去命令を受けることもあります。
⑦ 公園や道路沿いのベンチ・花壇

地域のために設置したベンチや花壇でも、道路上に設置する場合は占用許可が必要です。
設置後の維持管理者を誰にするかも大事なポイントです。
⑧ 工事現場の仮囲い・足場

建築工事でよく見かける足場や仮囲いも「一時的な道路占用」。
期間を区切って申請し、撤去後には報告書を出す必要があります。
⑨ 自販機やバス停のベンチ

実は自動販売機やバス停のベンチも占用物。
特に民間が設置する場合、道路管理者の許可が必要になります。景観条例の対象となる場合もあります。
⑩ お祭りやイベントの露店

地域イベントなどで道路を使うときは「一時占用許可」が必要。
歩行者天国や露店出店は、警察の「道路使用許可」とセットで申請するのが基本です。
道路占用が必要になる場面は身近にある
道路占用というと公共インフラの話のように感じますが、実際は日常生活にも関係しています。たとえば、家の前のちょっとした構造物や、地域活動の設備なども対象になることがあります。
「うちはちょっとだから大丈夫」と思っているうちに、後から指導を受けて撤去することになる例も少なくありません。
行政書士がサポートできること
○道路占用許可申請の書類作成
○現地調査・図面の添付
○自治体との事前協議サポート
○一時占用や更新申請の代行
道路占用は自治体ごとにルールや様式が異なります。正しく手続きを行うことで、安心して公共の道路を使うことができます。
まとめ
道路占用は、電柱や水道管だけでなく、植木鉢やポストなど身近なものも対象になります。
トラブルを防ぐためには、設置前に道路管理者へ確認し、必要に応じて行政書士へ相談しましょう。
身近な道路を安全に、そして適切に使うために── ちょっとした意識が大切です。
手続きは平日しかできないことも多くあります。
貴重な時間を割くよりも、行政書士くぼや事務所にお任せ!
どうぞお気軽に、お問い合わせください。